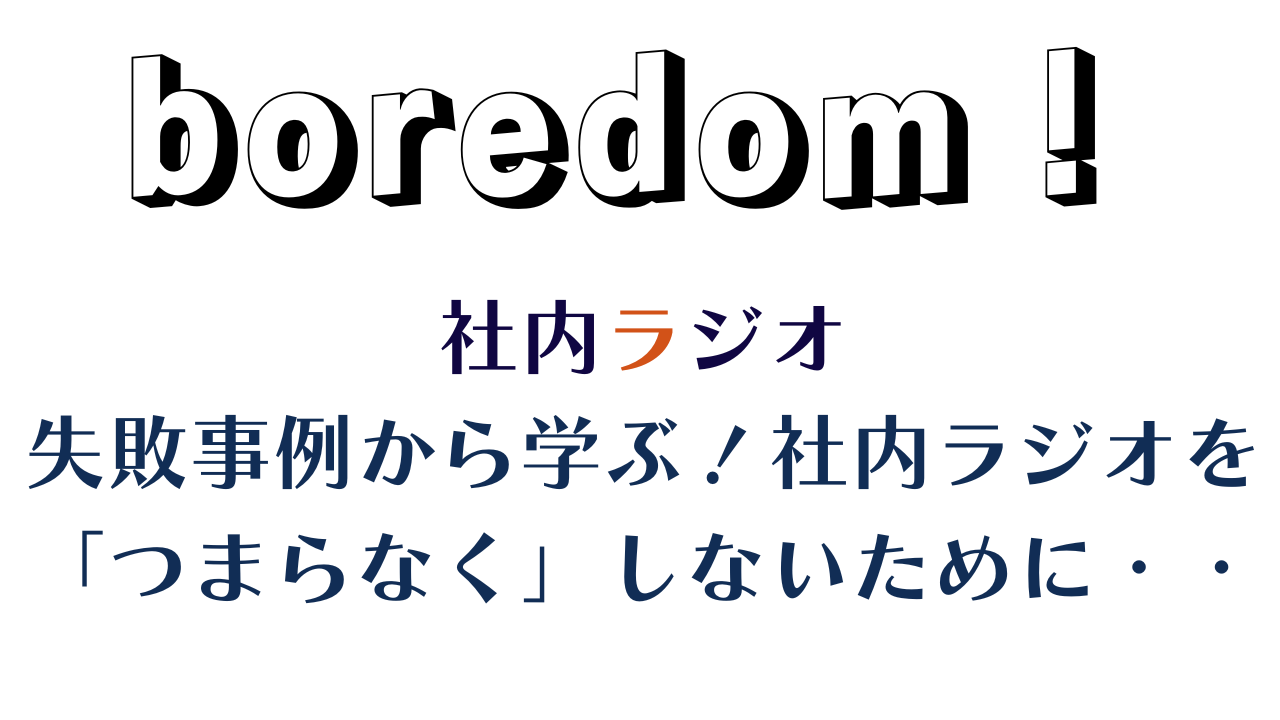訓示も「社内ラジオ」で!
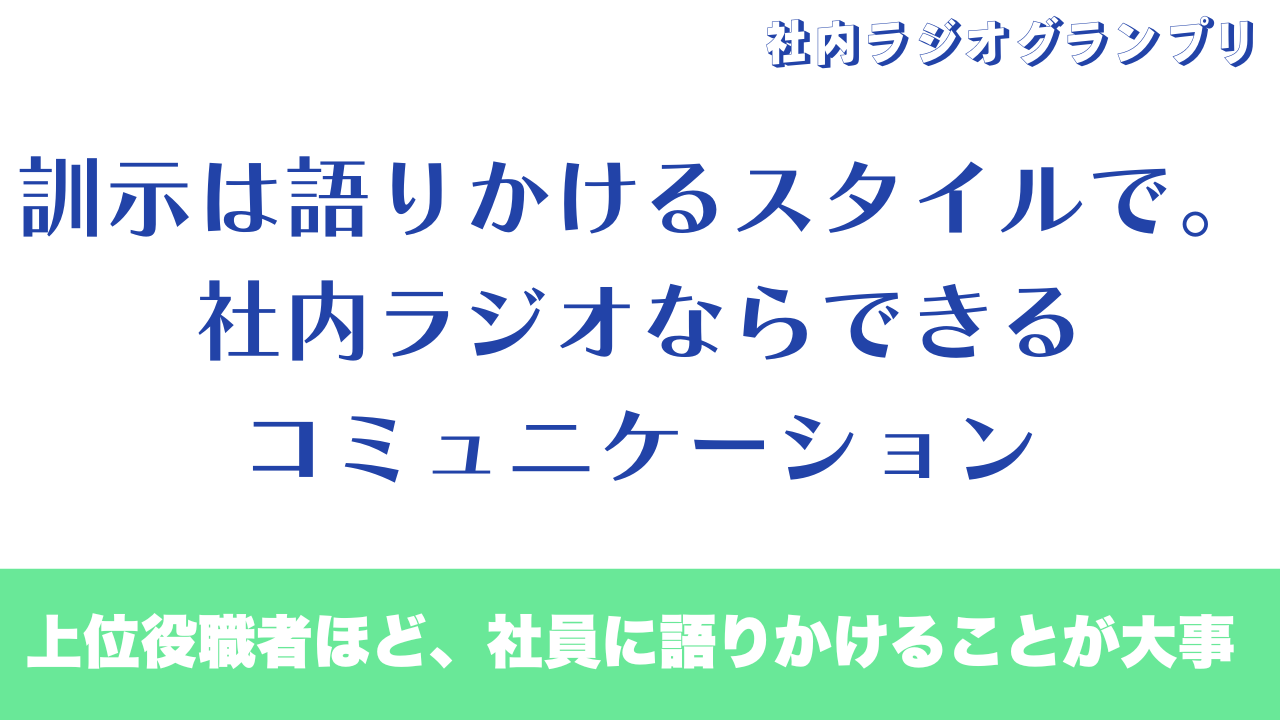
ああ訓示。されど訓示。
今年は年末年始のお休みが長かったせいか、エンジン再始動!に手こずった方も多いかもしれません。お休みから仕事モードに切り替えるのに一役買うのが、実は「新年の訓示」とかだったり。
会社員時代、「なぜこういうのがあるのか?」と思ってたんですが、今考えるとその役目が分かります。
記事を書いた人

堀 美和子
おもしろPR
プロデューサー
オンライン化必須の今ですから、かつてのように全員集まって聞くというスタイルだけでなく、リアルと配信ハイブリッド、或いは配信のみというパターンもありそうです。
しかし、届ける形は変わっても、中身が旧態依然の「まさに訓示」だったら、もったいないと思うんです。「訓示らしい訓示」って聞く方にしてみれば、あんまりWelcomeじゃありませんから、正直なところ。
せっかく「今年の目標」とか「事業計画」とか大事なことを直接話してもらっているというのに、なぜそうなるのか??一つは、意識の差があります。
自分の話を聞くのが当たり前と思っている。
聞くのが当たり前と思ってない。あくまでも業務の一環
それに由来するのが二つ目。「聞いて当然だ」(と思っている)と、「聞いてもらう工夫」があまりなされない。事業計画にしても今年の目標にしても、書類に書いてあることをそのまんま話してしまう。すると、おもしろくないから聞きたくならない。
二つの不都合を解消する一手が「社内ラジオ」。
不思議なことに、同じマイクに向かうのでも、「訓示」をする気で話すのと、「ラジオで語る」のとは違います。
なんとなくですがお分かり頂けますよね。前者は「今から話してやるからしっかり聞けよ」的に話す。しかし後者は「どうか聞き手に届きますように」と祈るような気持ちで話す。当然、どちらが届きやすくなるかは一目瞭然。
しかも「ラジオのDJやパーソナリティになった気で喋る」と、堅苦しい言葉って出てきにくいです。ラジオは話し手と聞き手の一対一。
目の前の誰かに話すように、マイクに向かって話すことになりますから、自ずとアンオフィシャルな雰囲気や気分になる。そうすると、どうですか?表情も言葉遣いも、柔らかく平易になる。実はそれこそ“聞いてもらう”ために最も大切なことの一つなんです。
聞き手と同じ地平に自分を置けるのが社内ラジオ
「訓示」というと、上(の者)から下(の者)へ、という印象が強いのに対して、社内ラジオは、話し手と聞き手が同じレベルになる。頭ごなしに言われるのと、さながら友人や知人の語りを聞くのと、どちらがいいですかと問われれば?
しかも「社内ラジオ」なら、ながら聞き・隙間聞きができます。人って案外、ふとした拍子に耳に入ってくる言葉を覚えます。そんな人間の生理を考えても、社内ラジオほど「訓示」にピッタリな媒体はないということに気づきます。
年度末・初は何かと「訓示」の機会が多い。これを機に社内ラジオを始めてみるのも良いと思います。始めるために、今まで話したことのない若手社員の手を借りる、なんてことも起こるかも。ますます社内の雰囲気が素敵になりそうです。