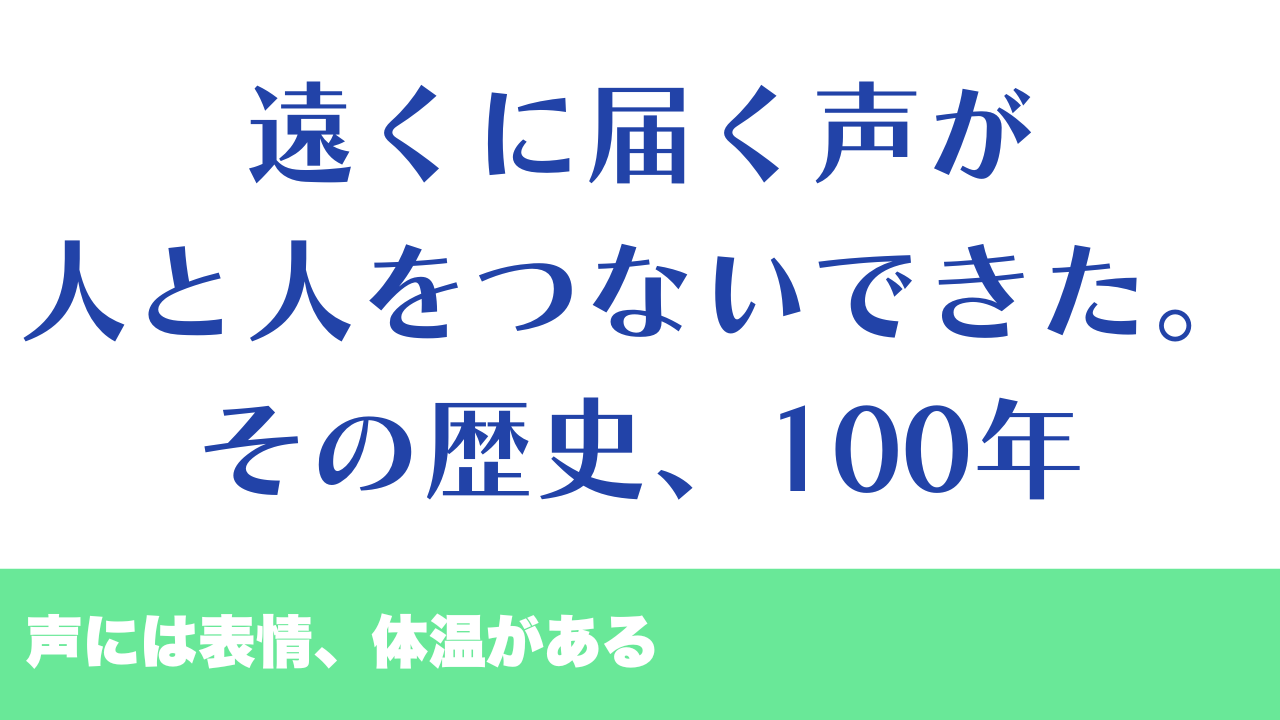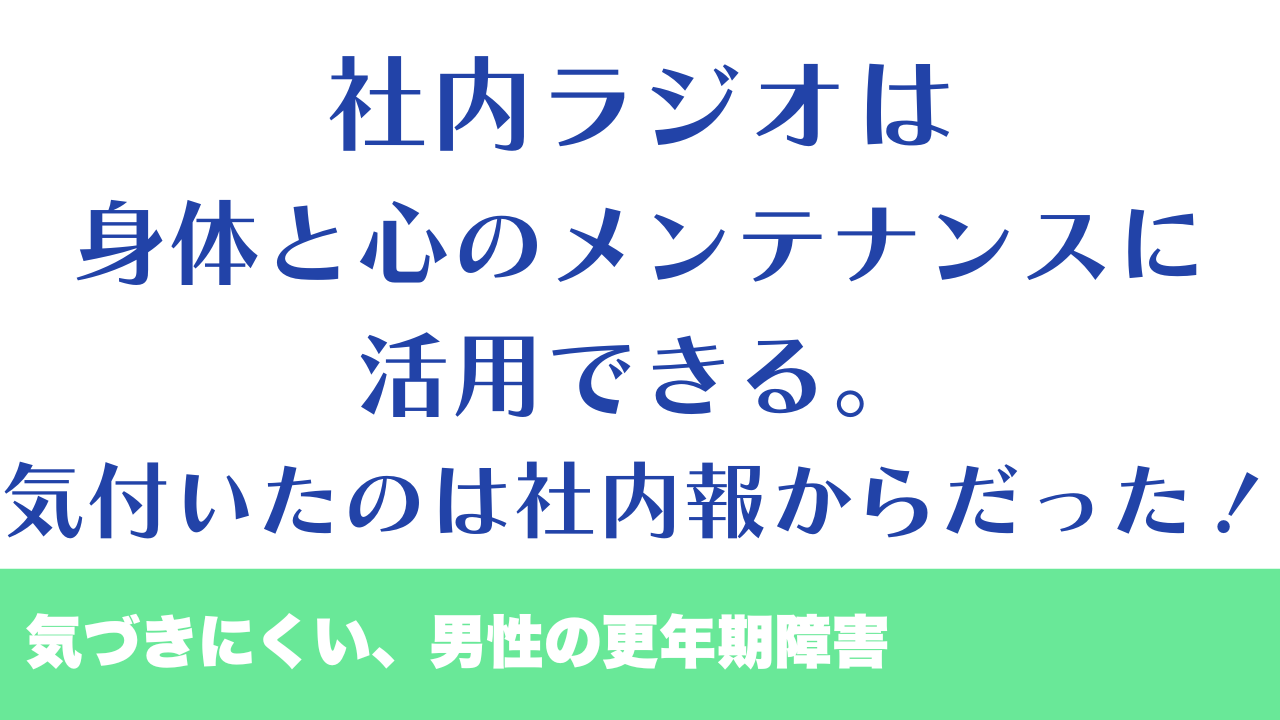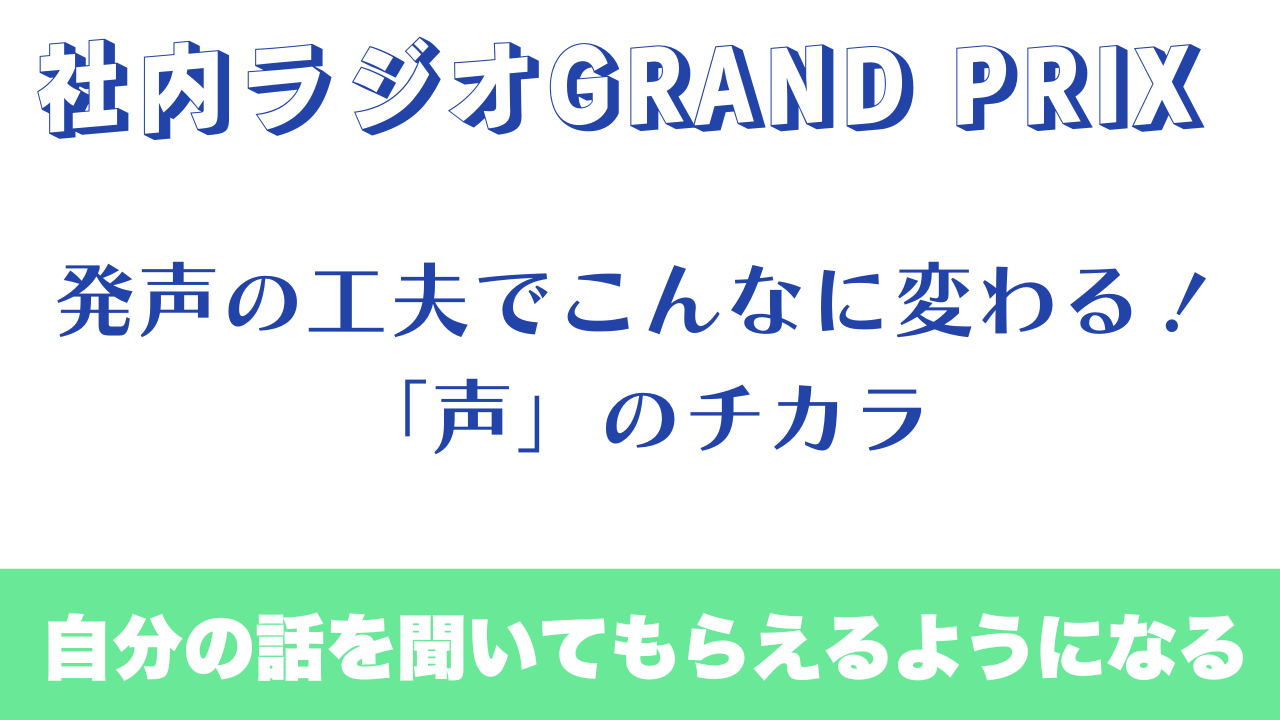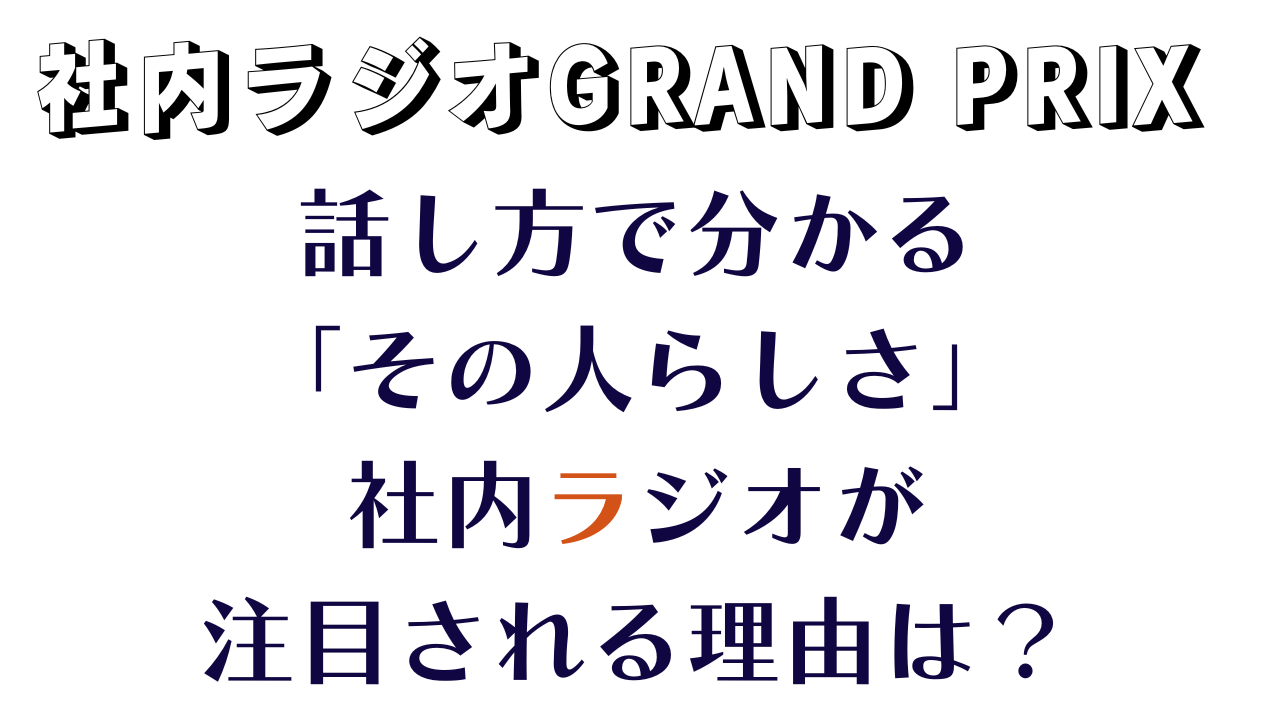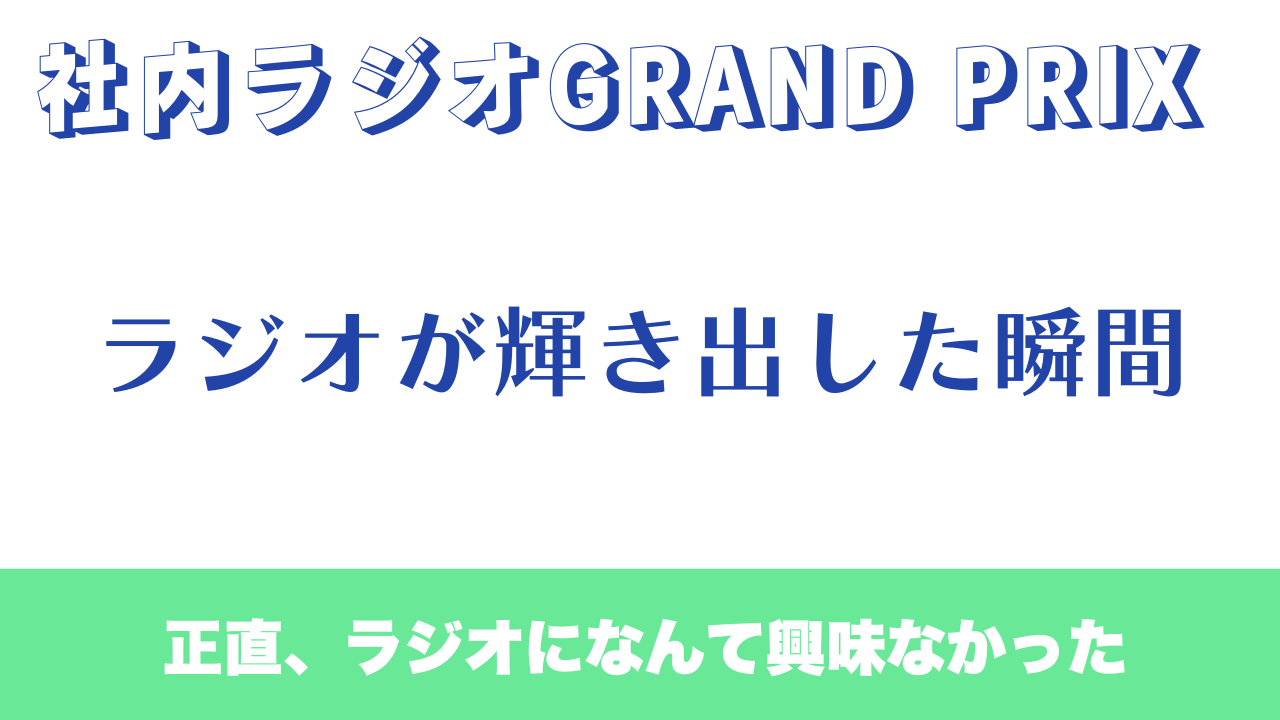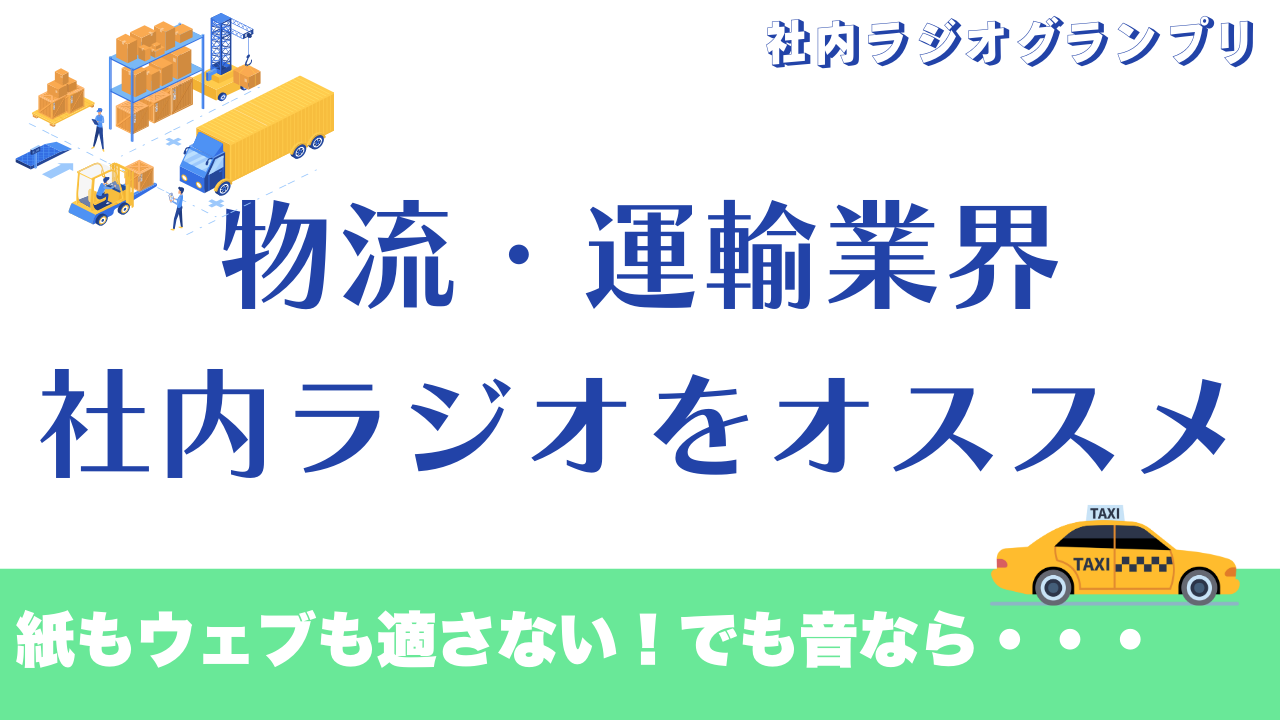社内ラジオ、聞いてもらうためのこれだけ!テクニック
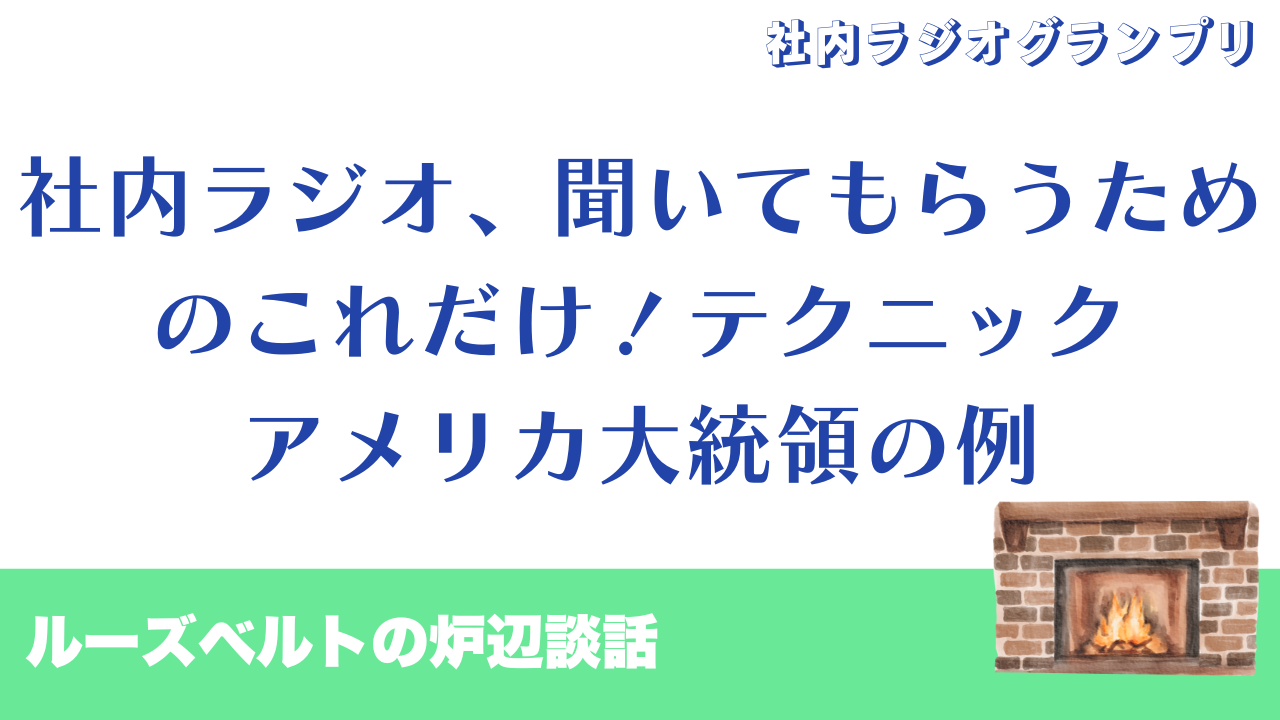
社内コミュニケーションツールとして「社内ラジオ」の注目が高まっています。社員同士の距離を縮めたり、経営層のメッセージをスムーズに伝えたりと、さまざまな活用方法がありますが、「社員にあまり聞いてもらっていない」と悩む担当者も多いです。この壁を乗り越えられるかどうかが本当に浸透するためにの第一関門です。
今回は、社内ラジオを成功させるために必要な「聞いてもらうためのポイント」をラジオをうまく活用した、ルーズベルト大統領の炉辺談話をヒントに考えてみます。
記事を書いた人

高間俊輔
株式会社オフィスエンニチ代表
ラジオはアメリカで始まった
まずはラジオの歴史を少し振り返ってみます。ラジオは今から100年以上前の1920年、アメリカのピッツバーグKDKA局が世界初の放送を行いました。当時、ラジオは民間企業による商業放送が中心でした。
一方、イギリスでは1922年にBBC(英国放送協会)が設立され、公共放送としての役割を果たしました。日本ではそれより少し遅れて1925年にラジオ放送が開始され、商業放送と公共放送の両輪で発展していきました。
政治にも利用された
ラジオは単なる娯楽ツールではなく、政治利用された歴史もあります。その代表的な例が、アメリカのフランクリン・ルーズベルト大統領による「炉辺談話(fireside chat)」です。
1930年代のアメリカは大恐慌の影響で多くの人々が不安を抱えていました。そんな中、ルーズベルトは、ラジオを通じて国民に直接語りかける「炉辺談話」を行っています。背景はニューディール政策を浸透されるための施策としてだった、という事は有名です。
この「炉辺談話(FiresideChat)」の特徴は、まるで「暖炉の前でくつろいでおしゃべりしているような親しみ」を感じさせる演出です。
彼の語り口は「ゆっくりと、はっきりと、温かみを込めた話し方」で、多くの国民が安心し、政策に耳を傾けました。演出は見事に成功しました。
特に、情報伝達ではなく、聞き手の気持ちを考えながら語りかける口調。このスタイルは社内ラジオにも応用できるポイントです。
聞いてもらう話し方のコツとは?
ルーズベルトの成功を振り返ると、「聞いてもらう話し方」は単なるテクニックではないことがわかります。「誰に向けて話しているのか」を具体的にイメージしているものと推測できます。
例えば、社内ラジオのターゲットが新入社員であれば、なるべく平易な言葉で、わかりやすく伝えることが重要です。
管理職を主なターゲットにするならば、すこし「このラジオを聞いて何が得られるのか」を明確に意識するなど。
具体的なテクニック
テクニックと書きましたが、テクニックと言うほどのことでもないんです。
具体的な誰かに話しかける意識を持つ
あなたが一人で語る場合は「具体的な誰か」がその場にいるように話します。対話形式だと、眼の前にいる聞き手とのトークで展開します。相手が語りやすくなる雰囲気作りをするのは、聞き手の役割です。
間(ま)を恐れない
話し手であるあなたは「間」が発生しても恐れないように。心から出てくる言葉を待つ間は重要です。放送ではありませんので、何十秒あいても「放送事故」にはなりません。
エピソードを交える
ただの情報伝達ではなく、エピソードを交えることで、臨場感に溢れた話になります。1対1だと、自然と相手に対してエピソードで語りかけていくので、面白くなりやすいです。エピソードを深めていく聞き手がいると、話し手は一気に話しやすくなるはずです。
まとめ
社員に社内ラジオを聞いてもらうには「親しみやすさ」を持って話し、聞き手が「自分に話しかけてくれている感じがある」と感じることは大事です。
ルーズベルト大統領の「炉辺談話」はプロパガンダですが、「親しみを込めて語りかける」部分は参考になります。
一人語りの場合は具体的な誰かを思い浮かべてみましょう。会話の場合は聞き手に向かって語りかけましょう。あなたの会社の社内ラジオのヒントにつながれば幸いです。