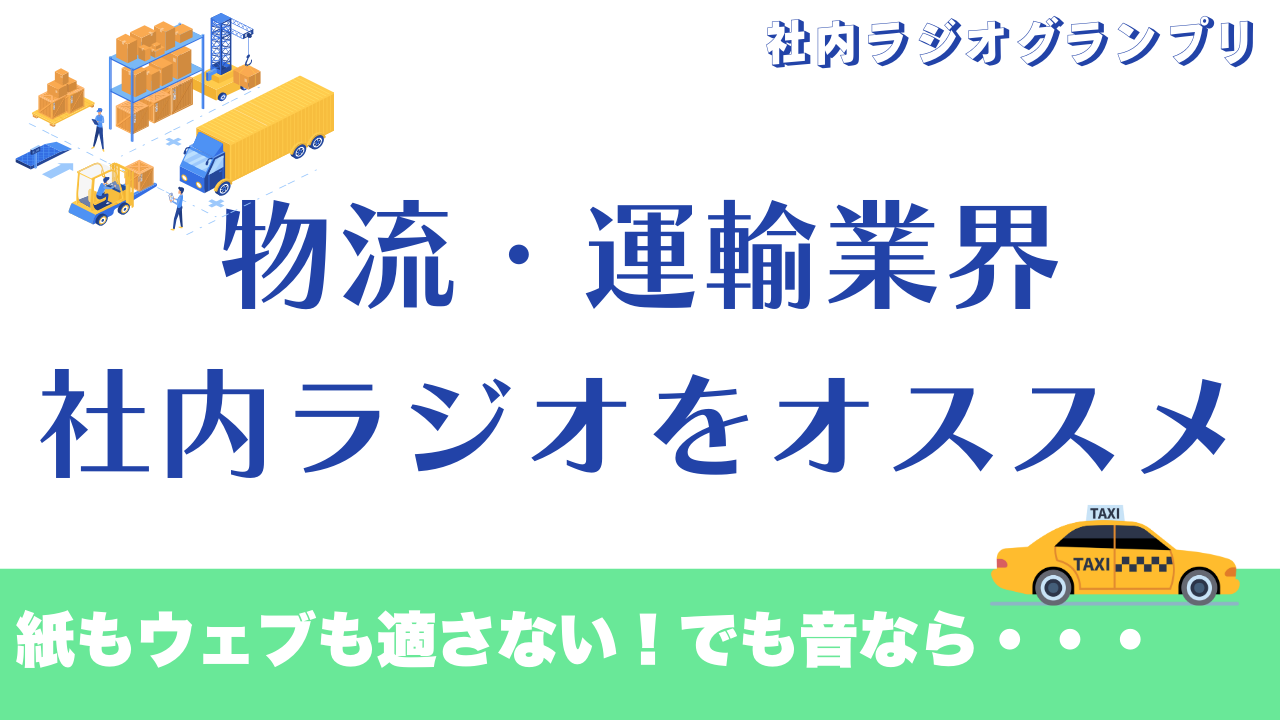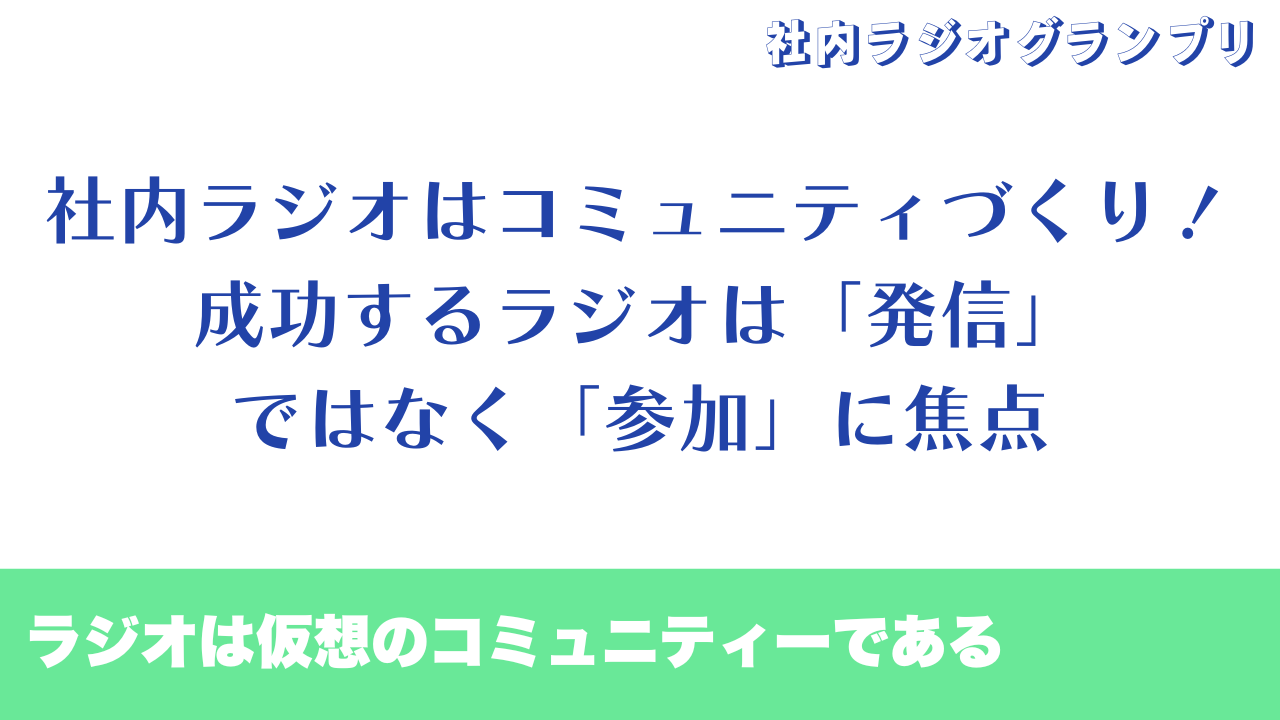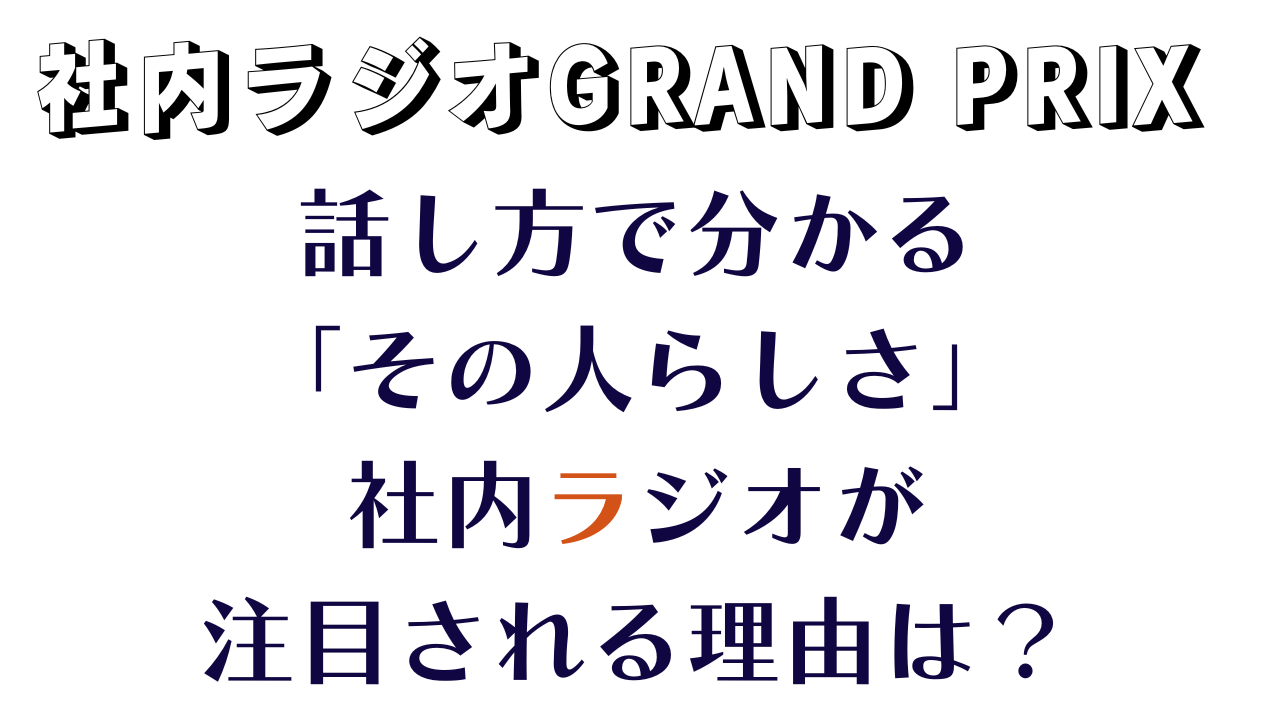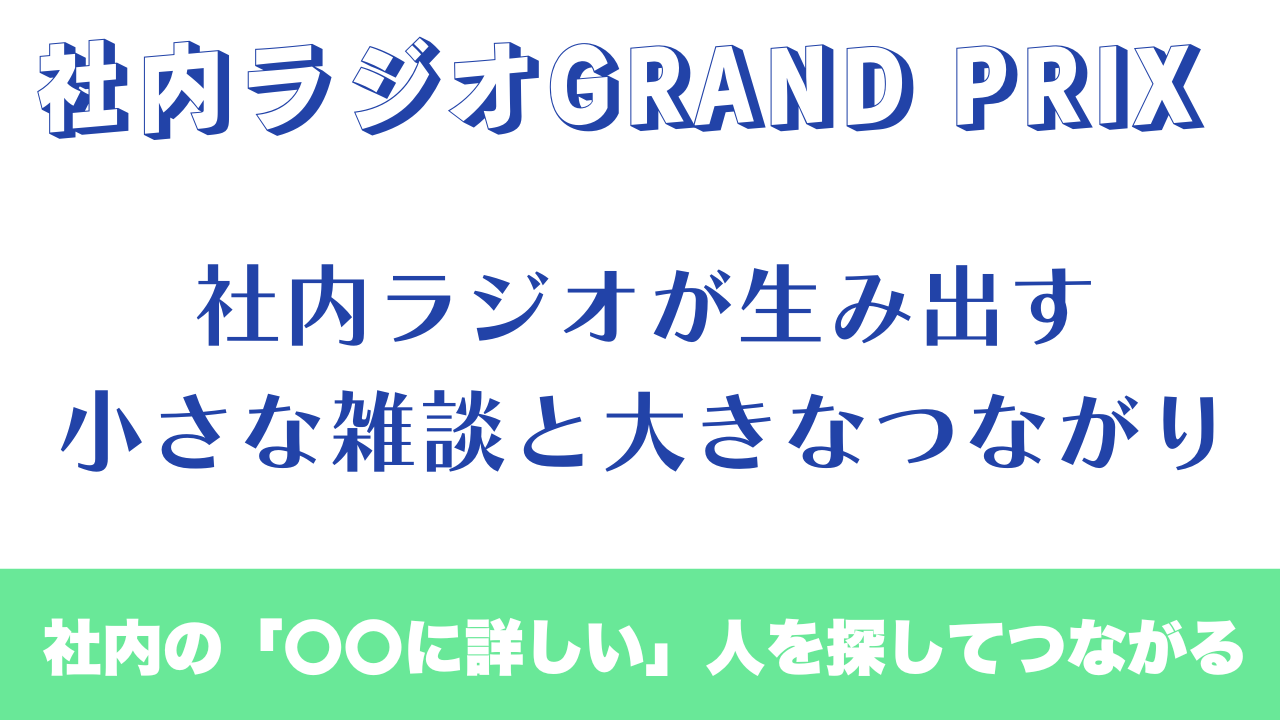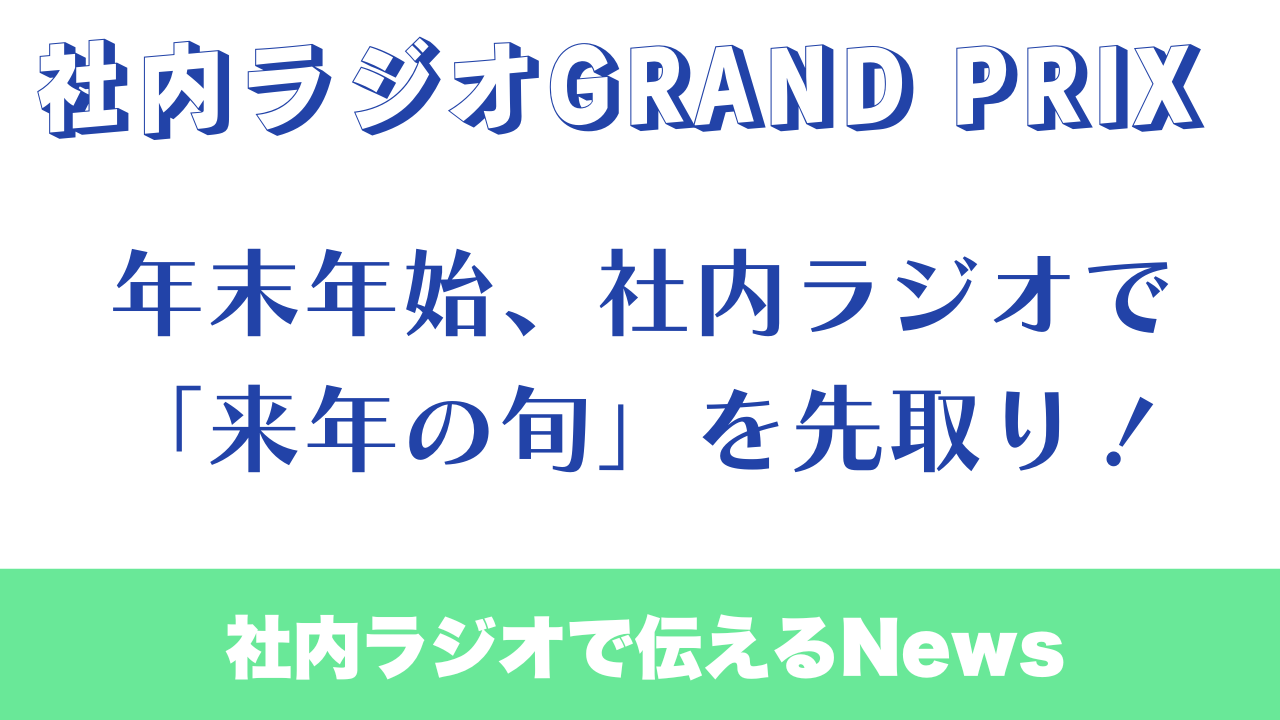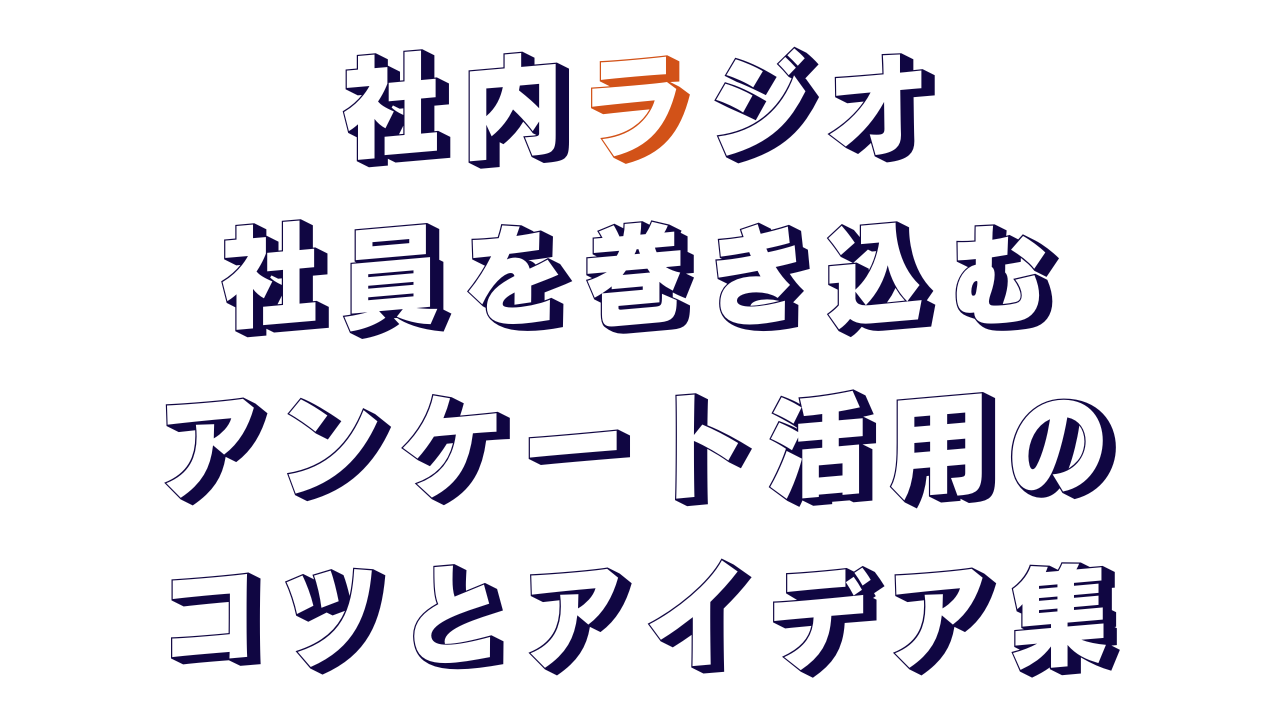声だからこそ残せる、伝えられることがある
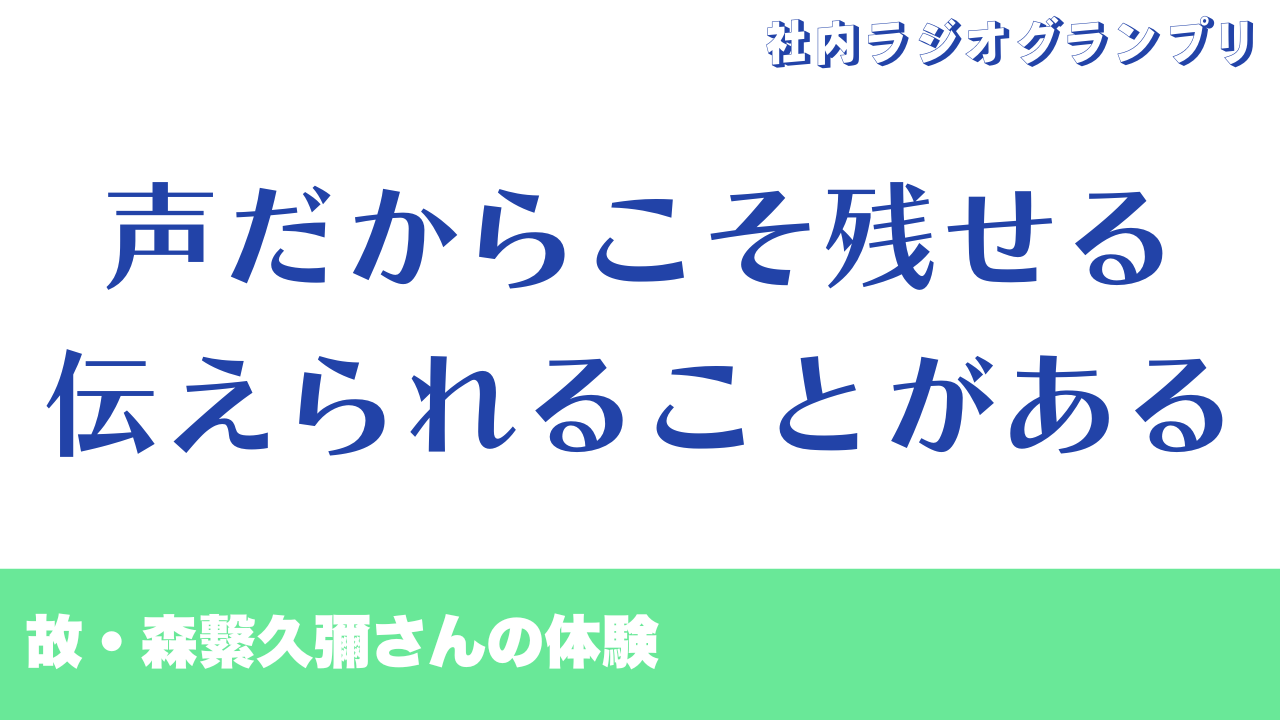
社内ラジオのエエとこをお伝えするのが本稿の旨。でも今日は、私が純粋に「声」についてしみじみしたお話を二つ、お取次ぎしたいと思います。
記事を書いた人

堀 美和子
おもしろPR
プロデューサー
語られないものを語るのが声。
一つ目は、故・森繫久彌さんの体験。『森繁久彌コレクション』の中の「青い海の底で」に収録されている一文、と朝日新聞の「天声人語」に書かれていました。
戦中、旧満州で放送局に勤めておられた森繫さんは軍の極秘命令で、特攻隊員の遺言を録音する仕事をされていたそうです。その中に一人、恐らく永久に忘れられない隊員がいた、と。
【ここから引用】
(前略)長い沈黙があったのち、白皙(はくせき)の若者はマイクに向かって、重い口を開いたそうだ▼お父さん。いま僕はなぜだか、お父さんと一緒にドジョウをとりにいったときの思い出だけで頭がいっぱいなんです。何年生だったかな。おぼえてますか。弟と3人でした。鉢山の裏の川でした。20年も生きてきて、いま最後に、こんな、ドジョウのことしか頭に浮かんでこないなんて……▼ポツンと言葉がとぎれてから、若者は言った。「何だかもの凄く怖いんです」。ハッと胸を刺されるような響きがその声にはこもっていた。「僕は卑怯かも知れません…ね…お父さんだけに僕の気持を解ってもらいたいん…だ」(後略)【引用ここまで】(2024.8.15朝日新聞より)
文字で伝えるには限界がありますが、でも、情景や、言葉では語りきれない「間」や、「なんともいえない感情」は、伝わってきます。声・音は、そんな“語られないもの”を語るんです。
もしあの時代、今みたいに映像(動画)ファーストでこのシーンが収録されていたとします。もちろん映像の方が伝えられる情報は百倍も二百倍も多い。
けれど、「ハッと胸を刺されるような響き」は、そこまで感じ取れないんじゃないかなと思いました。私見ですが。
絵のない声だけだからこそ、人は耳を澄ませて話し手を感じ取ろうとする。不思議なことに私達にはそういう能力というか気持ちが備わっているようです。
何気ないものほど、残す価値がある
二つ目は、「大阪中心」というWebサイトで紹介されている「映画興行発祥の地」。
下記のリンクをクリックして頂くと、左側に「語り部『映画のふるさとミナミ』」等々という音声コンテンツが出てきます。
https://tour.osaka-chushin.fun/spot/2115/
収録されたのは随分前とお聞きしています。でも、今聞いても古びてない。
恐らく、話し手さんは今はお年を召されてお声も変わっていらっしゃるかもしれない。ここまでのお話しもおできになりにくくなっているかもしれない。
それでも声で残っているがゆえに、“今”私はこれを聞けました。そして内容に聞きほれました。その時は当たり前のように話されていて、何気に残されたものかもしれないけれど、こんな良いものをよく語り残してくださったと、思わずにいられません。
社内ラジオとは時代も環境も違うコンテンツが教えてくれること
上に挙げた事例は、社内ラジオとは、もちろん時代も環境も違います。でも、多くのことを示唆してくれています。
もし私が社内ラジオの担当者だとしたら、近づく年度末、定年退職を控える方の声を順次収録していくかもしれない。そういう方々と若手社員の座談会を企画するかもしれない。
その時にしか残せない声や音。それをこそ後に継いでいくのが、社内ラジオの役目なのかも。